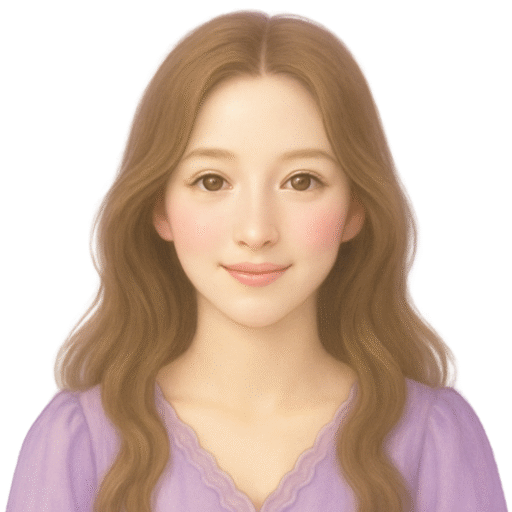「子どもが厄年を迎えるけど、お金を包んで渡すならいくらが妥当?」
そんな悩みを抱えて検索された方も多いのではないでしょうか。
厄年は人生の節目とされ、親から金銭や品物を渡すのは「無事に過ごしてほしい」という祈りを込める意味があります。
ただし、いくら渡すかについては明確な決まりはなく、一般的には5,000円〜30,000円程度が相場とされています。
この記事では、厄年に親から渡す金額の目安や、相場に合わせた選び方のポイントを解説!
また、現金以外におすすめの贈り方や、子どもの性格やライフスタイルに合わせた工夫も紹介しますので、きっと迷いが解消できるでしょう。
目次
厄年に親から金額を渡す意味とは?
厄年に親が子どもへ金銭を渡すのは、単なるお祝いではなく、「厄を落とし、無事に過ごしてほしい」という祈りを込める行為です。
お金は生活に直結するため象徴性が強く、古くから「厄払い」や「人生の節目を支える贈り物」として大切にされてきました。
金銭は「厄落とし」の象徴とされる
昔から日本では、お金を包んで渡すことには「厄を落とす」「穢れを流す」という意味合いがあります。
例えば、厄年に神社でご祈祷を受ける際も、御初穂料として金銭を納めますよね。
同じように、親から渡すお金は“お守り”のような役割を果たし、子どもに安心感を与えるのです。
節目を無事に過ごすための親心
厄年は「人生の転換点」であり、健康や生活面で注意が必要とされる時期です。
だからこそ、親がお金を渡すのは、「節目を無事に乗り越えてほしい」という親心の表れです。
具体的には、
- 厄払いの祈祷料に使ってほしい
- 健康のための品や生活の足しにしてほしい
- 気分を前向きに切り替えてほしい
といった願いが込められています。
金額そのものより気持ちが大切
厄年に渡す金額には明確な決まりはなく、大切なのは金額よりも気持ちです。
5千円でも、1万円でも、そこに「無事でいてほしい」という想いが込められていれば十分意味を持ちます。
むしろ、過度に高額すぎると子どもに気を使わせてしまうこともあります。
親からの金銭は「縁起物」や「祈りの形」として受け取ってもらえれば、それで良いのです。
厄年に親から渡す金額の相場
厄年に親が子どもへ金銭を渡すとき、いくらにすべきか悩む方は多いです。
実は決まった金額のルールはありませんが、一般的には1万円〜3万円程度が目安とされています。
ここからは、ライフスタイルや地域の違いによって変わる「金額の考え方」を解説します。
1万円〜3万円程度が一般的な目安
多くの家庭で選ばれているのが、1万円〜3万円前後です。
この金額帯は「厄払いの祈祷料」や「お守り・縁起物の購入」にも使いやすく、高すぎず低すぎない安心感のある額といえます。
例えば、
- 祈祷料に1万円
- 残りを本人の自由に使ってもらう
という形にすると、実用性と気持ちの両方を込められます。
成人して独立している子には少し多めに
子どもがすでに社会人として独立している場合は、2万円〜3万円程度にする家庭も多いです。
これは「家族の節目を改めて意識してほしい」という願いから。
ただし、金額が大きすぎると気を使わせてしまうので、あくまで「ささやかな支え」として渡すのが良いでしょう。
生活が安定している子どもには、現金よりも品物を添える工夫もおすすめです。
地域や家庭の考え方によっても差がある
厄年に関する風習や金額の相場は、地域や家庭の考え方によっても変わります。
例えば、関西では厄払いに手厚くお金を使う風習がある一方、関東では簡略化して気持ち程度に渡すケースも見られます。
また、親の考え方や経済状況によっても違って当然です。
大切なのは「他の家庭と比べない」こと。
あくまで自分たちの家族に合った形で渡すことが、最も自然で温かいやり方です。
金額以外の贈り方の工夫
厄年に渡すのは現金だけではありません。
金額にこだわりすぎず、ちょっとした工夫や気持ちを添えることで、贈り物はさらに特別な意味を持ちます。
ここでは、金額以外にできる工夫を3つご紹介します。
お守りや赤い小物を添えると縁起が良い
厄年には「赤いもの」が魔除けの象徴とされてきました。
そのため、現金と一緒に赤いハンカチ・ベルト・財布などの小物を添えると、縁起の良い贈り物になります。
また、神社で授与されるお守りや御札を一緒に渡すのもおすすめです。
現金と組み合わせることで、形ある安心感と精神的なお守りの両方をプレゼントできます。
ご祝儀袋やのし紙に「厄払い」の気持ちを込める
お金をそのまま渡すよりも、ご祝儀袋やのし紙に包んで渡す方が気持ちが伝わります。
表書きには「御厄除」「祈厄払い」など、前向きな言葉を選ぶと良いでしょう。
見た目を丁寧に整えることで、「大切な気持ちを込めた贈り物」であることが一目で伝わります。
小さな工夫ですが、受け取る側にとって印象がぐっと変わります。
金額より「親からの手紙」や言葉を添えると印象的
どれだけ金額を渡すかよりも、親からの気持ちをどう伝えるかの方が心に残ります。
例えば、
- 「無事に厄年を過ごせますように」
- 「健康と幸せを祈っています」
- 「いつも頑張っているね」
といった一言を手紙やカードに添えると、お金以上の温かい贈り物になります。
照れくさい場合でも、短い言葉を添えるだけで十分です。
厄年に親から金額を渡すときの注意点
厄年にお金を渡すのは、あくまで「お守り代わり」や「節目を応援する気持ち」を込めたものです。
しかし、渡し方を誤ると子どもに余計な負担を感じさせてしまうこともあります。
ここでは、注意しておきたい3つのポイントをまとめました。
高額すぎて子どもに負担を感じさせない
親としては「少しでも力になりたい」と思うものですが、あまりに高額なお金を渡すと子どもが気を使ってしまう可能性があります。
特に社会人として独立している場合、「返さなければ」「気をつかわせてしまった」と感じさせてしまうことも。
そのため、相場を踏まえて**無理のない範囲(1〜3万円程度)**を意識するのがおすすめです。
不吉とされる数字(金額の端数)を避ける
金額を包む際には、縁起の悪い数字や端数を避けるのが一般的です。
例えば、
- 「4」→「死」を連想させる
- 「9」→「苦」を連想させる
といった数字は避け、1万円、2万円、3万円のようにきりの良い金額にするのが安心です。
無理のない範囲で渡すことが大切
厄年のお金は「援助」や「仕送り」ではなく、あくまで気持ちを形にしたものです。
そのため、親自身が無理をしてまで高額を渡す必要はありません。
大切なのは、
- 「少額でも心を込めて渡す」
- 「金額にこだわらず、安心を与える」
という意識です。
親に負担がなければ、渡す側も受け取る側も心地よく感じられるでしょう。
親からの贈り物で気持ちを伝える方法
厄年に渡す金額や贈り物は、形式や相場だけでなく、**「気持ちをどう伝えるか」**が何より大切です。
ここでは、親から子へ気持ちを届けるための3つの工夫をご紹介します。
金額に正解はないことを理解する
まず知っておきたいのは、厄年に渡す金額に「正解」はないということです。
相場はあくまで目安であり、親子の関係性や家庭の状況によって自然に変わって当然です。
大切なのは「お金を通じて安心を届ける」という気持ち。
金額にとらわれすぎず、自分たちらしい形を選びましょう。
厄年は「家族の絆を深める機会」と捉える
厄年は不安を感じやすい時期ですが、親からの贈り物が家族の絆を強めるきっかけにもなります。
「応援しているよ」「元気で過ごしてね」と伝えるだけでも、子どもにとっては大きな安心感となります。
単なる金銭のやり取りではなく、家族の思いを共有する場と考えると、より温かみのある贈り物になります。
感謝や応援の言葉を一緒に届ける
最後に大切なのは、言葉を添えることです。
どんなに少額でも、手紙や一言のメッセージがあるだけで印象は大きく変わります。
例えば、
- 「健康で元気に過ごしてね」
- 「これからの人生も応援しています」
- 「いつも頑張っていて誇らしいよ」
といった言葉を添えると、子どもにとって心強い励ましになります。
金額や品物よりも、「親の想い」が一番の贈り物になるのです。
【まとめ】厄年の贈り物は「金額よりも気持ち」が大切
厄年に親から子どもへ金銭を渡すのは、単なるお祝いではなく、「厄を落として無事に過ごしてほしい」という祈りを込めた贈り物です。
一般的な相場は 1万円〜3万円程度 ですが、金額に明確な決まりはなく、家庭や地域によっても違います。
大切なのは「どれだけ渡すか」よりも、
- 気持ちのこもった適切な金額を選ぶこと
- お守りや赤い小物を添えて縁起を担ぐ工夫
- 言葉や手紙を添えて安心感を与えること
です。
つまり、厄年の贈り物は金額以上に「親の想い」を伝える行為。
無理のない範囲で心を込めて渡すことで、子どもにとっても忘れられない温かい支えとなるでしょう。