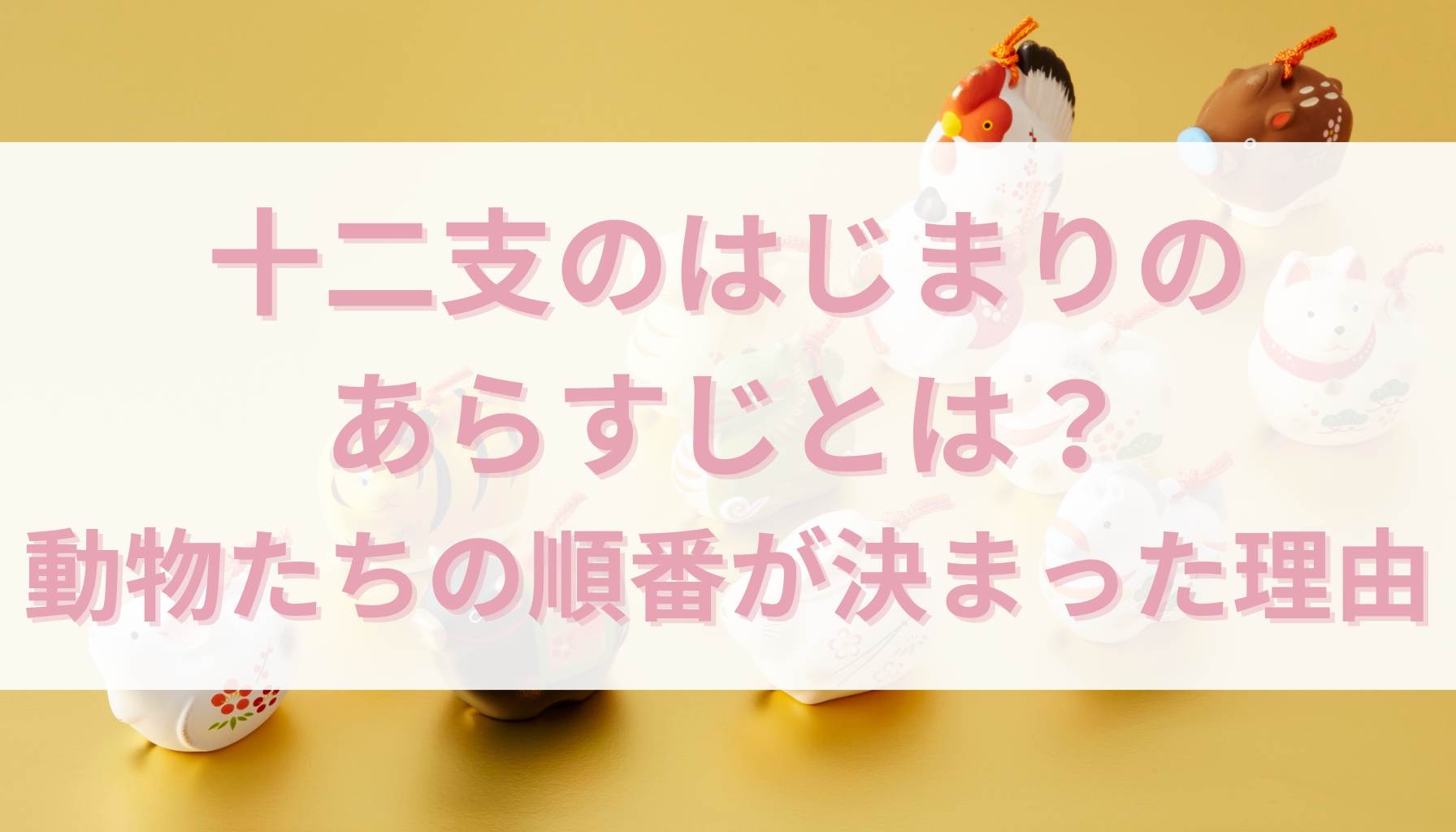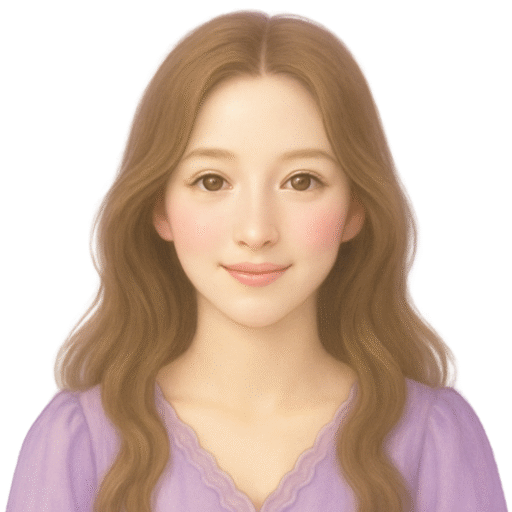「ねずみ年」「うし年」などで知られる十二支。
でも、どうしてこの順番なの?猫がいないのはなぜ?
この記事では、そんな素朴な疑問を、昔話をもとにやさしく解き明かしていきます。
干支の意味や動物たちの物語を知ると、お正月や年賀状がもっと楽しくなるかもしれませんよ?
目次
十二支のはじまりってどんな話?

十二支(じゅうにし)とは、12の動物で「年」を表す古い仕組みです。
ねずみ、うし、とら…と順番に動物が決まっていますが、どうしてその順番なのか気になりますよね。
実は、この順番は「神様が開いた大きな競争」の結果だったのです。
天帝(てんてい)や玉皇大帝(ぎょくこうたいてい)と呼ばれる神様が、「河(かわ)を越えて先に着いた12匹の動物を順番に年にあてる」と決めたのが始まりとされています。
先に着いたねずみ、うし、とら…というように、レースで使った順がそのまま、ねずみ年、うし年…というふうに並びました。
十二支とは?干支の意味と動物たちの紹介
十二支は、もともと「地支(ちし)」という12の数え方に、わかりやすく動物の名前を当てはめてできました 。
年だけでなく、月・日・時間にも使われ、それぞれの動物が持つ特徴が、性格・運勢に結びつけられることもあります 。
この12の動物は、ねずみ・うし・とら・うさぎ・たつ・へび・うま・ひつじ・さる・とり・いぬ・ぶたです。
十二支のはじまりに出てくる基本ストーリー
昔、大きな神様が「河を越えるレース」を開きました。12匹までが参加でき、先に着いた順に年に当てはめるというルールです 。
- ねずみが見事1番になったのは、 うしに乗って河を逃れ、ゴール直前に飛び降りて先に着いたから。
- うしは力強く泳いで2番目。
- とらは泳ぐ力で3番を獲得。
- うさぎは石や丸太を跳び渡って4番になりました。
その後も、竜やへびなどが順にゴールし、最後はいのししがのんびり遅れて12番となったのです。
このお話のポイントは、「知恵・力・協力・性格」の違いが結果に現れることです。
次は「どうしてその順番になったの?」「ねずみはなぜ1番?」などを深く見ていきますね。
なぜあの順番になったの?十二支の順番の決まり方
十二支になった動物たちの順番には、実はちゃんと意味があるのです。
それではどうしてその順番になったのか、順を追って見てみましょう。
動物たちが神様のもとへ競争することに
昔、天界の偉い神様(玉皇大帝)が、動物たちに「干支に入れるかどうかは、○○まで競争して順番を決めるぞ」と言いました。
場所は川の向こう岸へのレースです。
- 先に12の動物が川を渡ってゴールした順に、1番から12番までの順番が決まりました。
- これで子(ねずみ)→丑(うし)→寅(とら)…と決定されたわけです。
ねずみが一番になった驚きの理由
ねずみがなぜ1番になったのか?力が強いわけでも速いわけでもありませんでしたが、ある秘密の方法で勝ち取ったのです。
- ねずみは、川を渡るのが苦手なので、うしの背中にこっそり乗せてもらっていました。
- そしてゴール手前で「ぴょん」と飛び降りて、一番最初にゴールイン!
- うしはそのまま2番に。また、とらは力で3番、うさぎは丸太を跳び越えて4番…と続いていきました。
このように、賢く知恵を使うことで、小さなねずみでも大きな成果を出せるという教えも、このお話には含まれているわけです。
第3章では、他の動物たちがどんな方法で順位を獲得したのか、そしてなぜ猫が入っていないのかについてご紹介します。
十二支の物語に出てくる12の動物たちの役割
十二支の順番は、神様のもとへ行く「レース」で決まったというお話があるとお伝えしましたが、それぞれの動物たちには性格や特徴もあります。
物語では、その個性が面白く描かれています。
それぞれの動物が登場する場面と特徴
レースに参加した動物たちには、こんな性格や行動があったと言われています。
- ねずみ(子):小さくてすばしこい。うしの背中に乗るという知恵者。
- うし(丑):まじめでコツコツ。ゆっくりでも休まずに歩く努力家。
- とら(寅):力持ちで行動派。川も勢いよく飛び越える勇ましさ。
- うさぎ(卯):器用で身軽。川に丸太を浮かべて跳びながら進んだ。
- たつ(辰):唯一の空想上の動物。天を飛ぶ力があるが、他の動物に道を譲るやさしさを持つ。
- へび(巳):静かで知的。こっそり進み、するするとゴール。
- うま(午):元気でスピードがある。勢いよく走り抜けた。
- ひつじ(未):仲間想いで協力的。仲良くゴールを目指す。
- さる(申):器用で好奇心旺盛。岩をつたって進んだ。
- とり(酉):空を飛べるが、みんなと一緒に進んだ礼儀正しい存在。
- いぬ(戌):忠実でまじめ。友だちのさると争いながらも頑張った。
- いのしし(亥):まっすぐ突き進む。途中で休憩したが、最後にゴール。
猫が入っていない理由とねずみとの関係
物語には「猫」が登場しませんが、その理由にはねずみとの伝説があります。
- 神様が「元日に集まる」と言ったのに、ねずみは猫に「1日遅れ」とウソをついた。
- 猫は次の日に来てしまい、十二支に入れなかったのです。
- この出来事から「猫はねずみを追いかけるようになった」と言われています。
このお話には「油断しないこと」「正直であること」が大切という教えも込められています。
この昔話から学べることとは?
十二支の物語は、ただの昔話ではありません。動物たちの行動や性格を通して、私たちが毎日の生活に活かせる大切なことを教えてくれています。
知恵・努力・性格の違いが生む結果
十二支の順番は、単に足が速いとか力があるから決まったわけではありません。
- ねずみのように知恵を使えば、小さな体でも一番になれる。
- うしのようにコツコツと努力を重ねれば、結果がついてくる。
- たつのように思いやりを持てば、みんなに信頼される存在になれる。
このように、誰もが自分の力をどう活かすかで、結果が変わるのです。
友だちとの関係やマナーについて考えよう
このお話からは、人との関わり方や礼儀についても学べます。
- 猫にウソをついたねずみのように、ズルいことをすれば信頼を失う。
- ひつじやとりのように、仲間を思いやる心を持てば、まわりと良い関係が築ける。
つまり、競争よりも協力と優しさが大切だということを、動物たちは教えてくれているのです。
この昔話には、大人になっても役立つたくさんのヒントがつまっています。
次は、十二支の話が日本の文化にどう関わっているかを見ていきましょう。
十二支の物語が日本文化に与えている影響
十二支のストーリーは、ただの昔話ではありません。日本では文化や日常に深く根ざし、さまざまな場面で活用されています。
お正月や年賀状と干支のつながり
- お正月には、十二支の動物が描かれた年賀状を交換します。これは「今年も良い年になりますように」と願う日本ならではの風習です。
- 干支は暦(こよみ)や方角などにも使われ、農業や計画にも役立っていたとされています。
- 「年男・年女」と呼ばれる風習もあり、その年が自分の干支の人はお祝いされることが多いです。
十二支の順番が生活に生きている例
- 幼稚園や保育園では、子どもたちの座席表が干支の順番で並ぶことがあります。
- 干支を使ったカレンダーやグッズ、お守り、絵本も多く、子どもにも身近な存在です 。
- 地元の神社や地域行事では、干支の年にちなんだイベントや飾り物が登場します。
このように、十二支の物語は日本人の生活に溶け込んでおり、昔話を知っていると、季節の行事や文化がもっと楽しく感じられること間違いありません。
よくある質問:十二支のはじまりにまつわる疑問
干支は世界共通?
実は、干支は世界共通ではありません。
干支の文化は主に中国をはじめとするアジアの国々(日本・韓国・ベトナムなど)で広まっています。
- 中国では「ブタ年」があり、日本の「イノシシ年」と少し違うこともあります。
- 西洋では干支のような動物を使った年の数え方はなく、星座や黄道十二宮(おうどうじゅうにきゅう)が使われます。
つまり、干支はアジアの一部の文化に根づいた特別な暦の考え方なんです。
どうして猫は十二支にいないの?
「猫がいないのはなぜ?」とよく聞かれますが、それには昔話の中に理由があります。
- 神様が動物たちに「新年のあいさつは○月○日に来てね」と伝えたとき、猫はその日を忘れてしまい、ねずみに聞きました。
- ところが、ねずみはわざと違う日を教え、猫はあいさつに遅れてしまいました。
- そのせいで猫は十二支に入れなかった、というお話です。
この話が元になって、猫は干支に入っておらず、今でもねずみを追いかけるのかもしれませんね。
【まとめ】十二支のはじまりを知ると、毎年の干支がもっと楽しくなる
十二支の物語は、ただの昔話ではなく、動物たちの個性や行動から大切なことを学べるお話です。
- ねずみの知恵と工夫
- 牛のまじめさ
- 猫とのすれ違いが生んだユニークな関係
これらを知ることで、毎年の干支をもっと身近で楽しい存在に感じられるようになります。
また、干支は年賀状やカレンダーなど、日本の行事にも深く関わっています。
意味を知っていると、お正月の楽しみ方がぐっと広がりますよね。
ぜひ、これからも干支の動物たちに注目して、一年をポジティブにスタートしてみてください。
あなたの干支の意味も調べてみると、新たな発見があるかもしれません。