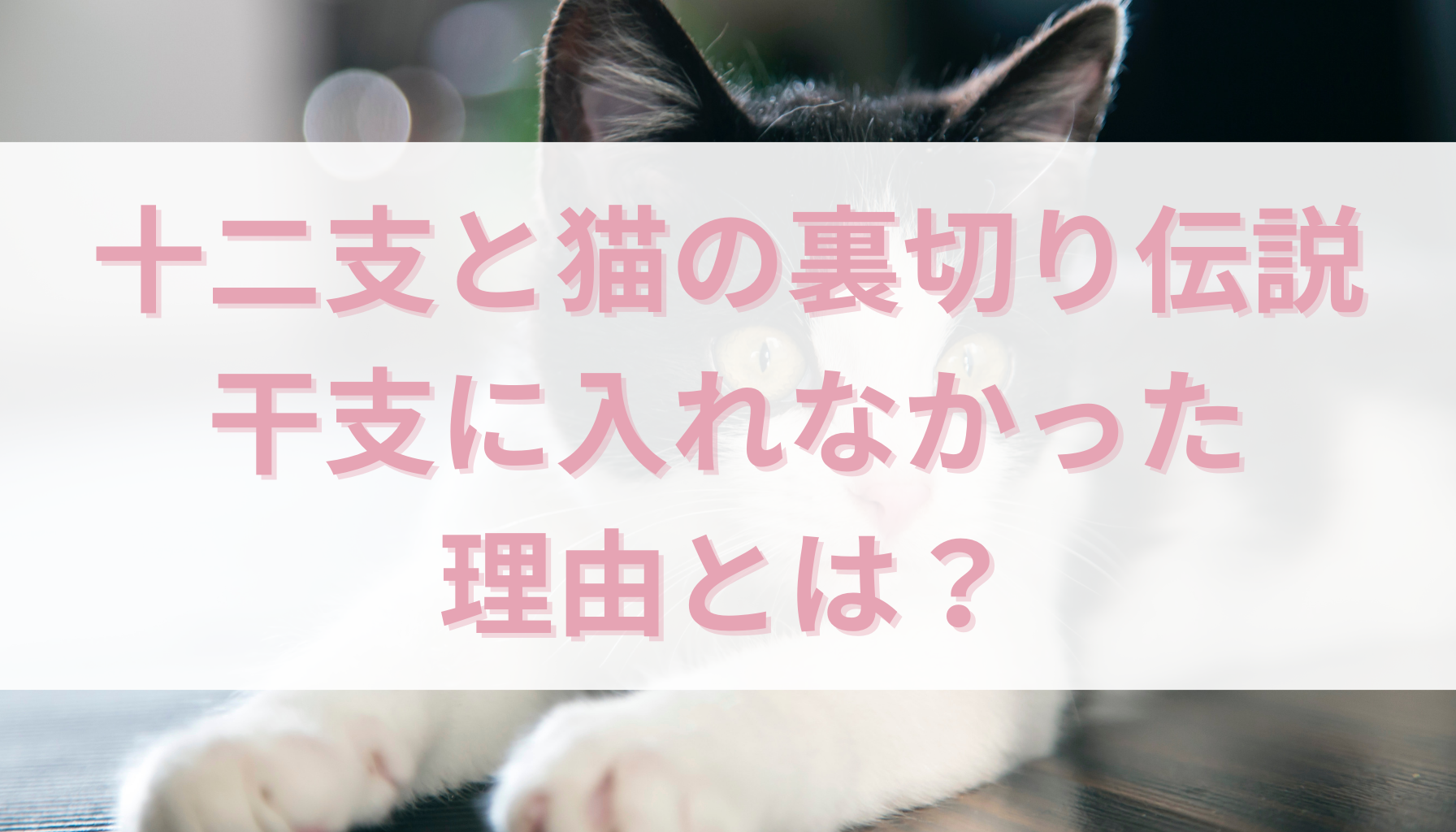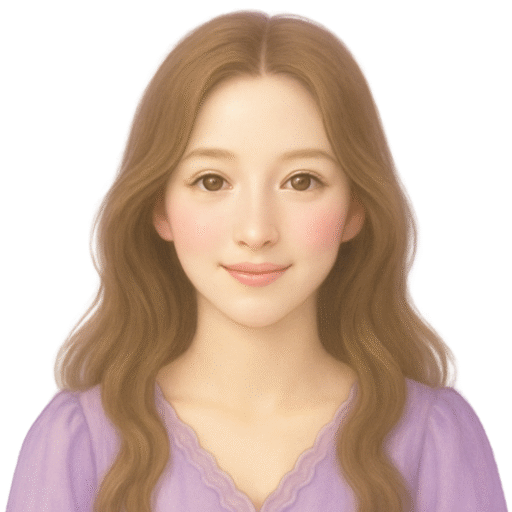「なぜ猫は十二支に入っていないの?」
そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか?
実は、猫が干支に入れなかった理由には、“裏切り伝説”として語り継がれるお話があります。
この記事では、その伝説や背景をやさしく紹介しながら、中国と日本の干支文化の違いにも触れていきます。
読み終える頃には、猫がもっと好きになっているかもしれませんよ。
目次
猫が干支に入れなかった理由とは?
「どうして猫は干支にいないの?」という疑問、実は多くの人が感じたことのあるテーマです。
結論から言うと、その理由には昔話として語られる“裏切り伝説”と、実際の歴史的背景の2つがあります。
この章ではまず、猫とネズミの物語にまつわる説、そして中国に猫がいなかったという現実的な理由を、わかりやすくご紹介します。
裏切り伝説に登場する猫とネズミ
猫が干支に入れなかった理由として、よく知られているのが「猫をネズミがだました」という**昔話(民話)**です。
これは日本をはじめ、アジア各地で語り継がれているお話です。ざっくりまとめるとこうなります:
- 神様が動物たちに「元日に来た順で干支にする」と伝える
- ネズミは猫に「1月2日だよ」とウソをつく
- 猫は1月2日に出発し、間に合わなかった
- 一方、ネズミは牛の背中に乗って先に到着し、見事“1番”に
こうして、猫は干支に入れず、ネズミを恨んで追いかけるようになった……というわけです。
実際にこの伝説が起源というわけではありませんが、干支に猫がいない理由を“物語”として伝える工夫だったのでしょう。
今でも「猫はネズミが嫌い」というイメージに、この昔話の影響が残っているのかもしれませんね。
現実的な理由は「中国に猫がいなかった」?
もうひとつの理由として、干支が生まれた当時の中国には猫がいなかったという説があります。
干支(十二支)は紀元前の中国・殷(いん)の時代に始まったとされますが、そのころ中国ではまだ猫が一般的な動物ではなかったと言われています。
猫が中国に伝わったのは、エジプトからの交流が進んだ後期で、**干支の動物が定着した時代には“まだ猫が身近にいなかった”**可能性があるのです。
一方で、イノシシ(中国ではブタ)やウシ、トラ、ウサギなどは、
- 農業や狩猟と深く関わっていた
- 日常的に人々の暮らしと関わっていた
という理由で、人々に馴染みのある動物が十二支に選ばれたと考えられています。
つまり、猫が入っていないのは「裏切り」ではなく、**当時の環境と文化の中で“自然に選ばれなかった”**という、現実的な理由もあるのです。
十二支と干支の基本をやさしく解説
猫がなぜいないのかを知るには、そもそも「十二支」や「干支」って何なのかを理解しておくことが大切です。
この章では、十二支の成り立ちや、干支との違いをやさしくおさらいしていきましょう。
十二支ってなに?干支とのちがいは?
まず、「十二支(じゅうにし)」とは、古代中国で生まれた時間や方角を表す記号のようなものです。
それぞれの支に動物が当てはめられて、今では「子・丑・寅…」でおなじみの干支(えと)として使われています。
【十二支の動物】
- 子(ね):ネズミ
- 丑(うし):ウシ
- 寅(とら):トラ
- 卯(う):ウサギ
- 辰(たつ):リュウ
- 巳(み):ヘビ
- 午(うま):ウマ
- 未(ひつじ):ヒツジ
- 申(さる):サル
- 酉(とり):トリ
- 戌(いぬ):イヌ
- 亥(い):イノシシ(中国ではブタ)
一方、「干支(かんし)」は、十干(じっかん)と十二支を組み合わせた60年周期の暦のこと。
私たちが普段「今年の干支は○○」と言っているのは、実は“十二支”だけのことを指しているんですね。
どうして動物が使われるようになったの?
十二支に動物が使われるようになった理由には、人々に覚えてもらいやすくするためという説があります。
本来は「子・丑・寅…」という文字が使われていましたが、これらは抽象的でわかりにくいため、それぞれに身近な動物を割り当てたというのが始まりです。
たとえば:
- 「子」にはすばしっこいネズミ
- 「丑」には力強いウシ
- 「寅」には勇ましいトラ
など、動物の性質やイメージが、その年の象徴としても使われるようになったのです。
こうして、十二支は単なる記号ではなく、人々の暮らしに根づいた文化の一部として、広く親しまれるようになったんですね。
中国と日本の干支文化の違い
「同じ干支なのに、猫の扱われ方が違うの?」と感じたことはありませんか?
実は、中国と日本では干支に対する考え方や猫の立ち位置に、文化的な違いが見られます。
この章では、それぞれの国で猫と干支がどのように関わってきたのかを見ていきましょう。
中国では猫と干支の関係は?
中国において、干支はもともと**「十干十二支」=暦を表す記号**として生まれました。
古代の中国では、暦・方角・時間・占いなど、さまざまな場面で使われていました。
では、なぜ猫がそこに含まれなかったのか?
主な理由は以下の通りです:
- 干支が成立した当時、中国にはまだ猫が広く普及していなかった
- 猫はエジプトやインドから後に伝わったとされ、干支の制度が確立された紀元前の時代には間に合わなかった
- 農耕に役立つ動物(牛・馬など)や、象徴的な存在(龍・虎など)が優先された
また、中国では猫は幸運の象徴として扱われることもありますが、干支としての重要性はあまりないとされています。
つまり、猫が干支に入っていないのは「除外された」というよりも、最初から“候補になかった”という歴史的背景が大きいのです。
日本では猫と干支をどうとらえている?
一方で、日本では猫は身近で親しまれる存在として、古くから人々に愛されています。
干支にこそ入っていませんが、「猫年があってもいいのに」と思う方も多いのではないでしょうか?
日本では、猫と干支の関係に対して次のような文化があります:
- 民話や昔話で「猫がネズミに裏切られた」という説話が語られている
- 干支に猫がいない理由を、「ネズミにだまされたから」と物語にして伝える地域もある
- 「猫の干支グッズ」や「非公式な“猫年”」など、親しみを込めて独自に楽しむ文化がある
また、現代の日本では、十二支の動物以外でも縁起を担ぐアイテムとして「招き猫」などが使われるようになり、
干支には入っていなくても“縁起が良い動物”として猫は高い人気を誇っています。
つまり日本では、「猫=裏切り者」ではなく、ちょっと切ないけど愛されキャラのような存在になっているのです。
なぜ猫は“裏切り者”とされるのか?
猫が干支に入らなかった理由としてよく語られる「裏切り説」。
でも本当に、猫が誰かを裏切ったのでしょうか?
この章では、猫とネズミの昔話の由来や、猫に対する誤解とその背景を見ていきます。
ネズミが猫をだました昔話の由来
もっとも有名なのは、神様が干支を決めるために動物たちに「元日に来なさい」と言った話です。
ここでネズミは、猫にわざと間違った日を教えます。
その流れを簡単にまとめると:
- 動物たちが干支入りをかけて神様のもとへ行く
- ネズミは猫に「来るのは1月2日だよ」と嘘をつく
- 猫は1日遅れで到着してしまい、干支に入れなかった
- それ以来、猫はネズミを恨んで追いかけるようになった
この話は日本のほか、中国やベトナム、タイなどにもバリエーションがあり、口伝えで広まった民話とされています。
つまり、「猫が裏切った」のではなく、むしろ“裏切られた側”なのです。
民話に見る猫のイメージと誤解
民話の中で猫は、少し「のんびり屋」「だまされやすい」キャラクターとして描かれることが多いです。
でも実際の猫は、鋭い感覚と自立した行動で知られる動物。
現代のイメージとは少しちがいますよね。
一方で、昔の人々にとって猫は:
- 夜行性で静かに行動する
- 表情が読みにくい
- 単独行動が多い
などの特徴から、**どこか“謎めいた存在”**に見えていたのかもしれません。
そうしたことから、裏切りや不運と結びつけられてしまったのでは?という見方もあります。
ただし、現代では「猫好き」の人がとても多く、干支に猫がいないことを残念がる声も多いため、
猫はむしろ**“選ばれなかったけれど、特別な存在”**として愛されていると言えます。
【まとめ】猫が干支にいない理由を知って楽しもう
猫が十二支に入っていない理由は、昔話の中で「ネズミに裏切られたから」と語られることが多いですが、
実際には当時の中国に猫が広く知られていなかったり、干支に使われる動物の基準に合わなかったりと、文化的・歴史的な背景が大きく関わっていました。
猫が干支にいないからといって、それが「不吉」「嫌われていた」というわけではありません。
むしろ現代では、猫はその自由な生き方や癒しの存在として、干支にいなくても特別な人気を持ち続けている動物です。
- 干支に猫がいない理由は民話と歴史の2つの視点がある
- 十二支は人々の暮らしと深くつながった文化
- 中国と日本で干支や猫への考え方が異なる
- 猫が“裏切り者”とされたのは物語上の設定にすぎない
干支をきっかけに、猫という動物の魅力や、文化の面白さを再発見できたらうれしいです。
「干支に猫がいないことも、なんだか猫らしくていいな」
そんなふうに感じてもらえたら、きっと猫も喜んでくれるかもしれませんね。