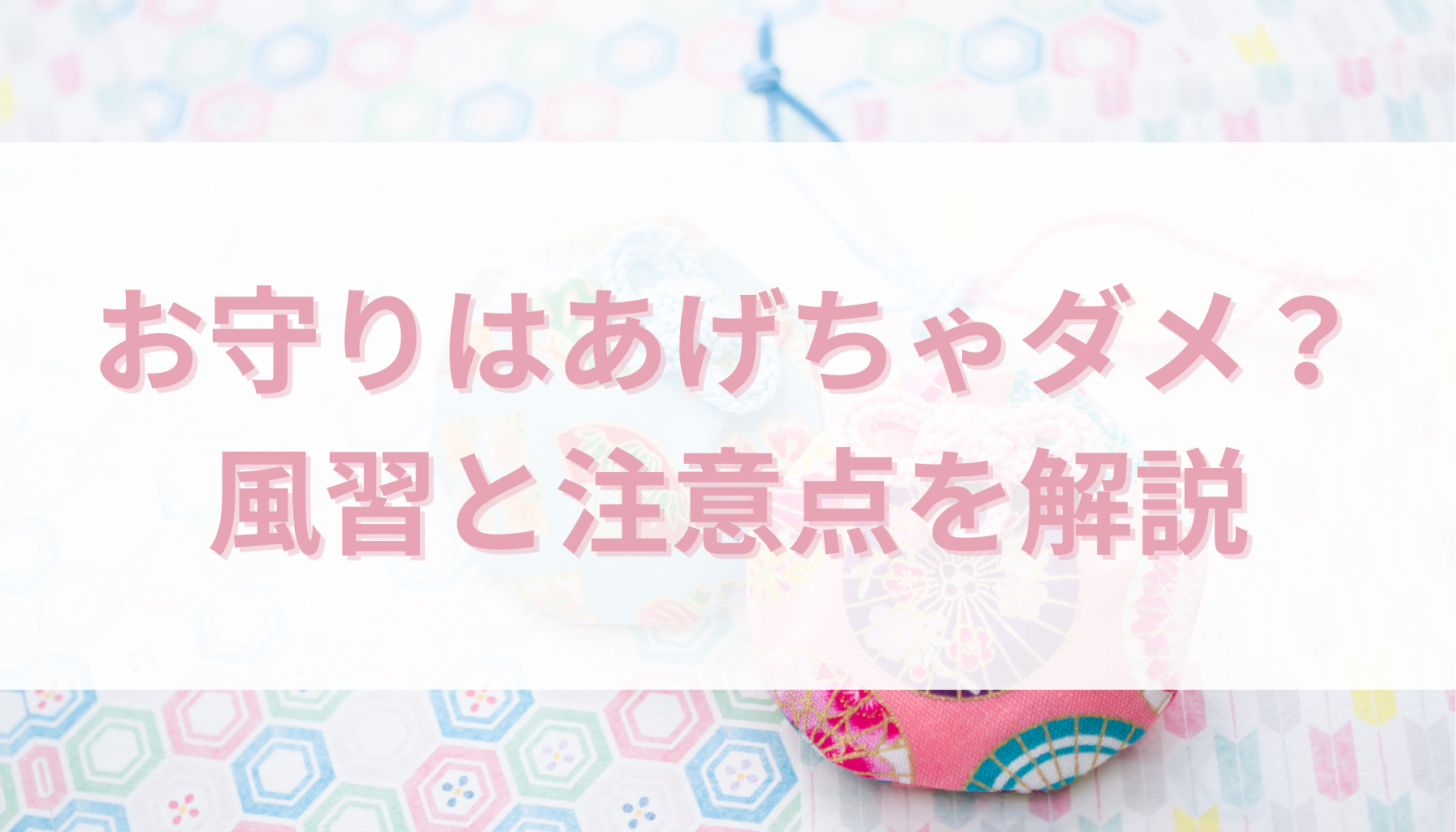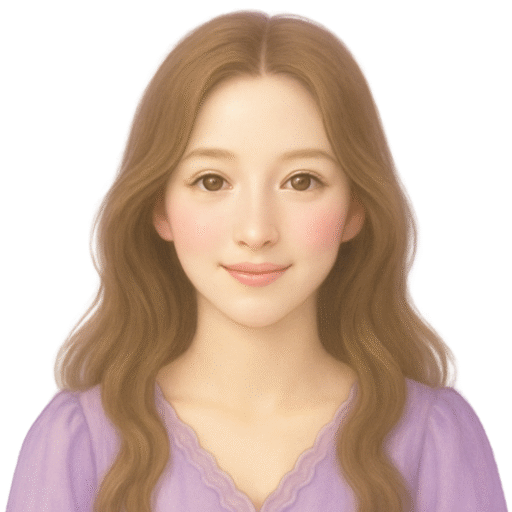「お守りって人にあげても大丈夫?」
そんな疑問を感じたことはありませんか?
実はお守りには、あげてはいけないとされる理由や風習があるんです。
この記事では、お守りを他人にあげるのがなぜダメなのか、その意味と注意点をわかりやすく解説していきます。
正しい扱い方を知って、大切な気持ちをよりよい形で伝えましょう。
目次
お守りをあげるのはダメって本当?
「お守りって人にあげたらダメって聞いたけど、どうして?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
お守りは、見た目には小さなお守り袋でも、実は“その人専用”の強い願いや祈りが込められている特別な存在なんです。
ここでは、まずお守りの本来の意味と、なぜ他人にあげるのが望ましくないとされているのかをご紹介していきます。
お守りの本来の意味とは?
お守りは、神社やお寺で授かる「加護(かご)」の象徴です。
多くの場合、自分の健康・安全・学業・仕事などの願いを込めて授かるものであり、持ち主のために祈祷されたものでもあります。
つまり、お守りはその人のために「神仏との縁を結ぶ媒介」になっているともいえるのです。
そのため、他人にあげてしまうと、その縁やご利益まで手放すことになると考えられています。
また、お守りには目に見えない“気”が宿っているとされ、その人の思いや願いと強く結びついているため、持ち主以外の人には合わないエネルギーになってしまうこともあるのです。
なぜ他人にあげるのがNGと言われるのか
お守りをあげることが「NG」とされる理由は、いくつかの風習や信仰的な背景にあります。
主な理由は以下のとおりです。
- 本来は「一人一体」のものとして扱うべき
- 神仏とのご縁を他人に渡してしまう行為になる
- 祈願された内容が他人に合わないことがある
- 相手が信仰を持っていない場合、負担になることも
とくに、「自分の災厄を人に押しつける」と誤解される場合があるため、知らずに渡してしまうと相手を不安にさせてしまうこともあります。
気持ちがこもっているものだからこそ、扱い方にも慎重さが求められるんですね。
お守りをあげることで起きやすいトラブル
「いいものだと思って渡したのに、なぜか気まずくなった…」
お守りは“良かれと思って”人に贈りたくなるものですが、実はそれが誤解や気持ちのすれ違いにつながるケースもあります。
ここでは、実際に起こりやすい2つのトラブルについてご紹介します。
気持ちがすれ違ってしまうことも
たとえば、「健康を祈ってるから」とお守りを渡したつもりでも、相手によってはこう感じることもあります。
- 「私の体調、そんなに心配されてた?」
- 「もしかして、私に悪いことが起きそうって思ってる?」
- 「もらってうれしいけど…重いかも」
このように、贈る側と受け取る側の気持ちにギャップが生まれることがあるのです。
また、信仰心や宗教観の違いがあると、お守り自体に抵抗感を持っている人もいます。
特に目上の人や距離感のある相手に渡すと、戸惑わせてしまうこともあるため注意が必要です。
運気の“譲渡”によるエネルギーの乱れ
お守りは、「自分のために神仏から授かった特別なもの」。
それを他人に渡すことで、自分の守護を手放すことになってしまうともいわれています。
また、お守りにこもったエネルギーは、その人の願いや“気”と深く結びついているため、別の人が持つと“エネルギーの違和感”が生まれる可能性も。
これが原因で、
- お守りを持ってから調子が悪くなった
- 気持ちが落ち着かない
- なんとなく合わない感じがする
といった感覚を覚える人もいます。
贈った側にとっては善意でも、受け取る人の運気や気分に影響を与えることもあるということを、心に留めておきたいですね。
お守りをあげても良い場合ってある?
「じゃあ、お守りは絶対にあげちゃいけないの?」
そう思った方もいるかもしれませんね。
でも実は、相手との関係性や場面によっては“例外”として受け入れられるケースもあるんです。
ここでは、お守りをあげても失礼にならないパターンと、その際に注意しておきたいポイントを解説します。
病気や受験など願掛けのシーンでは例外も
お守りをあげるのが許容されやすいのは、相手の状況が明確に“応援”を求めているときです。
たとえば、
- 大切な人が入院することになった
- 受験や就職活動を控えている
- 妊娠中で安産祈願のお守りを贈りたい
など、「がんばってほしい」「守られてほしい」と心から思うときは、応援の気持ちとして受け入れられやすい傾向にあります。
ただし、それでも“お守りそのものを渡す”というよりも、**その人のために改めて授かりに行くこと(新品のお守りを選ぶ)**が基本です。
贈るときに気をつけたい3つのこと
お守りを渡す際に気をつけたいポイントは以下の3つです。
- ① 新品を渡す(自分が使っていたものは避ける)
→ 他人のエネルギーが入ったものは避けたほうが安心です。 - ② 相手に“受け取っていいか”確認する
→ 信仰や気持ちの部分に配慮し、押しつけにならないように。 - ③ “願い”より“気持ち”を伝える
→ 「守ってくれるといいなと思って」など、重くならない表現を選ぶと受け取ってもらいやすくなります。
特に身近な人や家族への贈り物であれば、丁寧な気遣いが伝わり、むしろ喜ばれることもあります。
大切なのは、「お守りを渡すこと」ではなく、“どう渡すか”という気持ちの表現なんですね。
お守りをあげてしまったらどうする?
「知らずに人にお守りをあげてしまった…」
そう気づいたとき、不安になる方もいるかもしれません。
でも大丈夫。きちんと心を込めて対処すれば、気持ちも運気もリセットできます。
この章では、すでにお守りをあげてしまった場合の対処法と、感謝を込めてお守りを手放す方法をご紹介します。
相手に渡してしまった後の対処法
すでにお守りを渡してしまっている場合、まずは焦らず冷静に受け止めましょう。
重要なのは「不安になること」ではなく、気持ちを整えて感謝を伝えることです。
以下のような対応がおすすめです。
- 相手との関係性が近ければ「実はこういう意味があるみたいで…」とさりげなく共有する
- 相手に返してもらうことは求めず、「自分の気持ちとして贈った」と伝えることで混乱を避ける
- 「きっと気持ちは届いている」と、自分の中で気持ちを区切る
もし気になる場合は、自分自身のために新しくお守りを授かり直すのもおすすめです。
神様とのご縁は、心から願えばいつでもつなぎ直すことができますよ。
気持ちを込めて神社でお焚き上げする方法
もし、お守りを人にあげたあとで「やっぱり手放すのが気になる」と思った場合は、神社やお寺でお焚き上げをお願いするのもひとつの方法です。
お焚き上げとは、感謝の気持ちを込めてお守りをお返しし、浄化してもらう儀式のこと。
多くの神社では、古札納所(こさつのうしょ)という場所で受け付けてくれます。
ポイントは、
- 感謝の気持ちを込めて返納すること
- その神社のお守りは、できればその神社に返すこと
- 遠方なら郵送での返納を受け付けている場合もある
ということです。
「ごめんなさい」ではなく、「ありがとうございました」の気持ちで納めましょう。
そうすれば、お守りに込められたエネルギーはきちんと浄化され、運気も整っていきます。
【まとめ】お守りの扱い方を大切にしよう
お守りは、小さな袋の中に「祈り」や「ご縁」が込められた、特別な存在です。
だからこそ、気軽に人にあげるものではないとされているんですね。
この記事では、
- お守りを他人にあげてはいけない理由
- 実際に起きやすいトラブルや誤解
- 例外としてあげても良いケースと注意点
- 渡してしまったときの対処法
について、やさしく丁寧にお伝えしました。
お守りは「気持ち」が大切。
大切な誰かに何かを届けたいと思ったときは、その人のために新しくお守りを授かるという方法もあります。
正しい知識をもって、神仏とのご縁を大切にしながら、自分も相手も心地よくなる選択をしていきましょう。